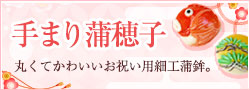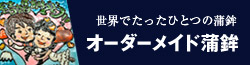2025.03.21
かまぼこの原料魚11種の味や食感の違いを解説
かまぼこは高タンパク低脂肪で、さまざまな栄養素が含まれています。
このため、健康やダイエットに興味のある方やアスリートからも注目を集めている食材です。また、”アシ”と呼ばれる独特な弾力があるので食感も楽しむこともできます。これらの特徴は、かまぼこの原料に秘密があります。
今回は、かまぼこの原料について詳しく解説していきます。
かまぼこの味や食感は原料の魚で変わる
かまぼこの原料は白身魚や赤身魚の魚肉をミンチ状にしたものです。かまぼこに適した風味と加熱すると生まれる弾力性を持ち合わせている魚が少ないため、一般的には数種類の魚を組み合わせてつくります。
白身魚を使ったかまぼこは、淡白な味わいと弾力性があります。一方、赤身魚を使ったかまぼこは、味が濃厚でうまみが強く、白身魚より柔らかい食感が特徴です。
かまぼこの原料となる魚
かまぼこの原料は地域やお店によって使用する種類が異なるため、風味や食感のバリエーションがとても豊富です。河内屋では原料にこだわり、スケトウダラ、シログチ(グチ)、イトヨリダイなどの上級グレードのすり身にこだわり、特注でオーダーし調達しています。
ここからは、かまぼこの原料である魚の種類について紹介していきます。
スケトウダラ


スケトウダラはかまぼこの原料として最もポピュラーで多くの地域で主原料として使用されています。北太平洋に広く生息するタラ科の魚で、体長は最大約90cm。体色は背中が灰褐色、腹側は銀白色。大きな口と下あごのひげが特徴。
肉質は柔らかく、白身で淡白な味わいで、低脂肪で高タンパク、ビタミンB群やビタミンD、ミネラル(リン、セレン)が豊富です。すり身やちくわの原料として利用され、卵はタラコや明太子に加工されます。
シログチ(グチ)
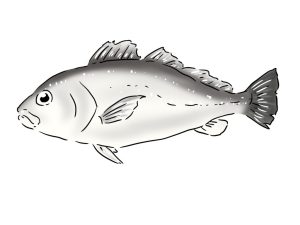

シログチはグチとも呼ばれ、体色は銀白色で口内が白色であることからシログチと名付けられています。日本近海の浅場~中深場に広く生息し、各地で水揚げされる食用魚。大きさは30cm前後で、脂肪分が少なく良質のタンパク質を多く含み、必須アミノ酸をはじめ、うまみ成分であるグルタミン酸も豊富で、香りと強い旨みが特徴的な白身魚です。
また、かまぼこの独特な弾力である”アシ”をつくるためにはなくてはならない原料で、主に高級かまぼこに多く用いられており、河内屋でもブレンドしている原料です。
イトヨリダイ
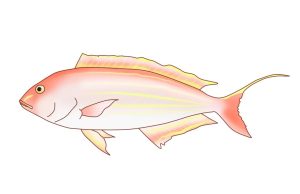

イトヨリダイは、名前に「鯛」とつくものの、タイ科ではなく、イトヨリダイ科に属する魚です。体形はやや細長く、体色は腹部が淡いピンク色で背側は青みも混じったような濃いピンク色が特徴。主な産地は西日本で、特に長崎県や熊本県、山口県で多く水揚げされていて、旬の時期は産卵期が終わる秋口の9月頃から春先までです。
旨みが強く身が柔らかいため、鮮度の良いものは刺身で食べられることもあり、料亭などで高級食材として振る舞われています。クセが無く味わい深い出汁が出ることから、河内屋でもかまぼこの原料としてブレンドしています。
ハモ


ハモは高級食材として知られており、てんぷらや煮つけなどによく利用されますが、関西では一部の高級かまぼこの原料として利用されています。体は細長い円筒形でウナギやウミヘビのような見た目をしてます。
一般的なサイズは全長1mで体色はお腹の部分が銀白色で、背中の部分は黒みがかっています。主産地は徳島県、大分県、山口県、兵庫県などの西日本の瀬戸内海沿岸で兵庫県での漁獲量は全国でもトップクラスです。
ふっくらとした身が特徴の白身魚で、ビタミン類をはじめ、カルシウムやリン、マグネシウムなどといったミネラルも豊富に含んでいます。
ホッケ
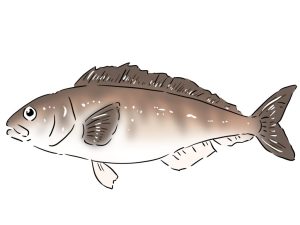

ホッケはクセがなくほどよい脂のりで、身の締まりがよく味が濃いのが特徴の白身魚です。鮮度が落ちるのが早いため、多くは開きの干物に加工されます。
国内の主な産地は北海道、青森県、石川県、山形県、新潟県などで、中でも国産ほっけの約9割は北海道で水揚げされており、北海道ではかまぼこの原料として使用するお店もあります。また、ホッケには良質なタンパク質、ビタミン、ミネラル、オメガ3脂肪酸であるEPAとDHAなど、さまざまな栄養素が含まれています。
タチウオ


富山をはじめ全国で獲れる白身魚で、主な産地は、愛媛、長崎、和歌山、大分、鹿児島などです。
スズキ目サバ亜目タチウオ科に属する魚で、全長は約1.5mに達し、白銀色の体と鋭い歯が特徴で、海釣りでも人気があります。韓国でも人気が高く国民食の一種となっています。
現在はかまぼこの原料として使っているお店は少ないですが、上品な味わいと濃厚な旨みがあり、塩焼き、煮付け、天ぷら、唐揚げなど、さまざまな方法で調理できます。
ヨシキリザメ
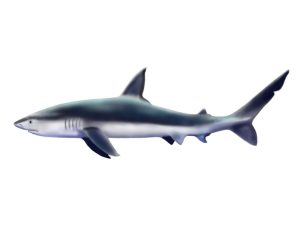
おでんでお馴染みのはんぺんですが、実はかまぼこの一種でもあります。はんぺんは、ヨシキリザメなどのすり身と山芋を原料に気泡をたくさん抱き込ませたゆでかまぼこです。
ヨシキリザメは宮城県気仙沼で、漁獲量の約8割が水揚げされており、漁獲量の多いサメの一種です。鮮やかな青色の体色と、長い頭部、大きく真っ黒な目が特徴で、中華料理の高級食材で知られるフカヒレでも使用されています。
キントキダイ


流通量が少なく、かまぼこの原料としては高価な部類で、生息地は青森県、宮城県、相模湾~九州南岸の太平洋沿岸、瀬戸内海、佐渡島~九州西岸の日本海・東シナ海と広域です。
脂がのっていて旨み豊かな白身魚です。鮮やかな赤い体色で、皮は硬く、さらにざらざらした硬い鱗に覆われていますが、中身は柔らかで美しい白身。調理方法は、焼き物、煮付け、フライ、刺身としてもとても美味しく、干物、すり身にも加工されます。
アジ


アジは大衆魚の一種で北海道から九州、沖縄までの日本各地の沿岸に分布しており、長崎県や島根県での水揚げ量が多い赤身魚です。長崎県ではあじ巻かまぼこや揚げかまぼこの原料として使用されています。
アジは、脂肪と旨みをたっぷりと含んだ独特の味とふっくらとした身が特徴で、たんぱく質、脂肪、ビタミン、カルシウムなどの多くの栄養素がバランスよく含まれています。調理方法は、たたきや刺し身、酢の物、塩焼き、フライ、煮物、つみれなど多彩です。
マイワシ
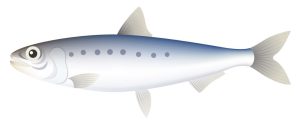

マイワシの漁獲量の日本一は茨城県で、千葉県、福島県、宮城県でも多く水揚げされています。
脂があり柔らかい食感で、かまぼこの原料として使用される以外にも、刺し身や焼いたり揚げたり、叩いてつみれにしたりと、幅広い食べ方で楽しむことができる赤身魚です。また、栄養価も高く、DHAやEPAをはじめとするオメガ3脂肪酸を豊富に含んでいます。
エソ
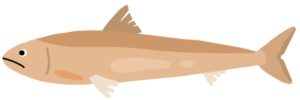

エソは熱帯、亜熱帯海域を中心に生息する魚で、日本近海では、千葉県から九州南岸の太平洋沿岸、若狭湾から九州南岸の日本海、東シナ海、瀬戸内海に生息しています。水深100メートルより浅い砂地や岩礁に生息しています。
エソのすり身は適度な弾力をもち、旨みが強く、美しい白さを保つというかまぼこに必要な条件を満たしており、高級かまぼこの原料として使用されています。
ホタルジャコ
水深35~130メートルのやや深い海に生息する小型種で、千葉県~九州、瀬戸内海など日本国内に広く分布しています。ホタルのように光ることから「ホタルジャコ」と呼ばれ、ホタルジャコを原料とする愛媛名物「じゃこ天」は揚げかまぼこの一種です。
骨と皮ごとすり身にしたじゃこ天は、カルシウムが豊富で栄養価が高いのが特徴です。
かまぼこ作りの工程
ここからは、かまぼこの作り方を6ステップに分けて紹介していきます。
【ステップ1】魚をすり身にする
-
- 原料となる数種類の魚肉をミンチ状にしてブレンドします。
- 河内屋では上級グレードのすり身にこだわり、特注でオーダーし調達しています。
【ステップ2】水や調味料を加える
-
- 水・塩・調味料などを加えます。
- そこからよく練り上げてすり身を完成させます。
【ステップ3】成型する
-
- 機械を使用したり、職人が手作業で成型したりなど、かまぼこの種類によって成型方法は異なります。
- すり身の中に空気が入らないよう、丁寧に成型します。
【ステップ4】蒸す
-
- すり身を1日ねかせて翌日に蒸すことで、食感に違いを出している商品もあります。
- 商品の種類によって、高温で一気に蒸したり、低温でじっくり蒸したりします。
【ステップ5】揚げる/焼く
-
- 蒸して完成のかまぼこもありますが、商品によっては、蒸した後に揚げたり、焼いたりする工程があります。
- 同じすり身でも、揚げたり焼いたりすることで違った食感や風味になります。
【ステップ6】真空包装して完成
-
- できあがったかまぼこは、カットした後に真空包装します。
- 河内屋では、包装されたかまぼこは全て加熱処理をして、殺菌をしています。
かまぼこの製造方法はこちらの記事で詳しく紹介していますので是非ご覧ください
かまぼこの作り方を解説!基本的な製法から河内屋のこだわりまで
原料魚の違いを意識してかまぼこを食べ比べてみよう
原料魚によってかまぼこの味わいや食感は大きく変わり、それぞれの特徴を楽しむことができます。どれも異なる魅力を持っていますので、食べ比べを通して、自分のお気に入りのかまぼこを見つけるのも楽しいですし、普段食べているかまぼこの新たな一面を発見できるかもしれません。
かまぼこを食べることで、魚本来の味わいや食文化の奥深さを改めて感じることができるのではないでしょうか。